本文
令和7年度 第2回「のべおか里山塾」が開催されました!!
鳥獣被害の解決や狩猟者の育成、自然や動物と人間の営みとの調和を図るための集落づくりについて学ぶ、令和7年度「第2回のべおか里山塾」が令和7年10月18日(土曜)~19日(日曜)に延岡市北川町及び北浦町で行われました。今回は、鳥獣対策の講義やくくりワナ仕掛け研修を行い被害対策について理解を深めました。併せて、ロボットを活用した稲作支援研修も行いました。また、宮崎大学農学部の学生による山間地域における鳥獣対策の共同研究成果発表会も行われ、学生目線での鳥獣対策も提案され、充実した「第2回のべおか里山塾」となりました。今回は、兵庫県や福岡県などからの参加があり57名が受講されました。
1.鳥獣対策基礎講座
- 講義
獣害対策の考え方と手法(イノシシ対策)
講師:農研機構 畜産研究部門研究推進部 動物行動管理研究領域動物行動管理グループ主任研究員 竹内 正彦 氏

【鳥獣被害が起こる理由】
- 野生鳥獣は生きるために常にエサを探していて、農作物は最高のエサとなっている。
- 集落(農地)に行けば柿や栗など収穫されない放任果樹の実があり、野生鳥獣の恰好のエサとなっていて、栄養価の高いエサとなっている。
- 農作物の残渣を野山に捨てることで野生鳥獣のエサとなり、集落に野生鳥獣を引き付けいている原因になっている。
- 今日の産業の変化により野生鳥獣が集落や農地に出やすい生活環境となっている。
【被害対策】
- 被害対策としては、「収穫農作物の残渣を農地内に放置しない」、「放棄農地を出来るだけなくす」、「放任果樹や収穫予定の無い農作物を無くす」など、野生鳥獣のエサ場となる環境を無くすこと。
- 農地等に隣接している原野など、野生鳥獣の住処となる藪などを切り開き、野生鳥獣が出にくい空間を確保する。
- 野生鳥獣の「追い払い」を継続して集落全体で取り組み、集落内で「追い払い」のルールを作り、自分の農地を守るのではなく、集落を守るという意識を持つことが大事。
- 被害対策について集落全体で合意形成の場を持って、被害を他人事とせずに集落みんなで被害を減らすことが必要。
2.くくりワナ仕掛け研修
- 講義、実技
講師:ファーミングサポート北海道 理事 原田 勝男 氏
【くくりワナ捕獲(講義)】
- 野生鳥獣の生息域や行動(獣道)を正しく理解し、ワナ免許の取得など、法令を遵守して捕獲を行うこと。
- ワナ設置後は見回りを行い、捕獲後は自治体の処分方法に従い、適正に処理すること。

【くくりワナ捕獲(実技)】
- 農家等の被害や要望に基づき、現地での野生鳥獣の生息場所や移動経路等を推測すること。
- 山林のどの方向から農地等に出没しているか、獣道を把握、確認しくくりワナを設置すること。
- くくりワナ設置後は、有害駆除によるワナ設置の許可証を必ず近くの立ち木等に表示すること。
(獣道の把握)

(くくりワナ仕掛け)

3.宮崎大学農学部共同研究成果発表会
令和7年5月から山間地域における鳥獣被害対策について、宮崎大学農学部学生(13名)及び三菱電機(株)統合デザイン研究所、延岡市との連携により延岡市祝子川地区(山間地域)における鳥獣被害について共同研究に取り組み、第2回のべおか里山塾において、鳥獣被害対策の提案を行う成果発表会を行いました。
【事前研修】
◆5月~7月
- 共同研究テーマの検討や鳥獣被害の現状等を理解する事前研修を実施。
◆8月
- 宮崎大学農学部学生13名(森林環境持続性科学コース10名、動植物資源生命科学コース3名)、坂本信介教授、平田令子教授が参加し8月27日(水曜)~8月29日(金曜)まで、2泊3日の日程で延岡市祝子川地区において、鳥獣被害のフィールドワークや地元農家との意見交換、鳥獣被害の対策を検討しました。
≪地元農家からの鳥獣被害の説明≫
≪鳥獣被害のフィールドワーク≫
≪地元農家への鳥獣対策の説明・意見交換≫
≪鳥獣対策ワークショップ≫
≪鳥獣対策発表会事前プレゼン≫
≪自然豊かな清流祝子川 全員集合≫
≪祝子川温泉参加者全員での記念撮影≫
【成果発表会】
◆10月18日(土曜)第2回のべおか里山塾
A班:テーマ「水田におけるイノシシへの直接的な対策」

『現状』
- 音やロケット花火などで追い払いをしているが、イノシシが慣れてくると効果が低くなる。
『発想(着眼点)』
- 侵入防止柵のイノシシ侵入個所を竹櫛等で塞いだら侵入が無くなったとのことから、イノシシから水田の作物を見えなくすることで農作物を守れるのではないか。
『取組の課題』
- 竹で覆うことはトタンで覆うのと比べ劣化も早いので、継続的な整備が必要で大変。
- かなりの労働力が必要となる。
『改善策』
- 竹に、自然に優しく環境負荷がない防腐剤を施して農地周りを覆うことで、長期間にわたり侵入防止につながるのではないか。
- 竹は自然に生えてくるので、経済的な負担が少なく、少ない経費で対策が実施できる。
B班:テーマ「イノシカ対策カメラで検証!」

『現状』
- イノシシやシカがどのように農地に侵入しているか見えてこない。(見える化が必要)
『発想(着眼点)』
- イノシシなどの行動を把握することで被害対策につながるので、カメラを設置してイノシシの行動を把握し大学で分析することで被害対策につながるのではないか。
- カメラを設置してイノシシがどのように侵入するか掴むことが被害対策のカギではないか。
『取組の課題』
- カメラ映像などのデータが膨大となり、その分析に時間と労力が必要となる。
- 設置できるカメラにも台数の制限があり、その費用やデータ送信量にも限界がある。
『期待される効果』
- カメラ映像を活用することで、効率的なイノシシ対策につなげることができる。
- イノシシの行動データを集め整理することで、被害対策の検討につながる。
C班:テーマ「SNS大作戦~Shika Nobeoka Shishi」

『現状』
- 山間地域は人口減、それに伴い農地を見守る人が少なく、動物が農地に安心して近づきやすく農作物被害が発生している。
『発想(着眼点)』
- 鳥獣被害を減らすため、SNSを活用して地域の活気を取り戻し、それらを通じて鳥獣被害対策につなげてはどうか。
- 全国から鳥獣被害についてSNSを通じてアドバイスをもらい対策に活用してはどうか。
- 最低限、スマートフォンがあれば取組が可能である。
『取組の課題』
- 継続した動画の投稿やSNSを運営できるのか。
- 祝子川地区の交通の不便さをどう解決して地域に多くの人を呼び寄せるか。
『改善策』
- 動画の提供、編集について専門業者からアドバイスをいただき、負担の少ない仕組みづくりを構築する。
- センサーカメラ映像やタイムプラスを活用して無人で撮影される映像を活用する。
- 交通の不便さ解消として、クラウドファンディングを活用し、祝子地区までの交通費の協力をお願いする。
【講評・感想】祝子川地区 小野 信介 様
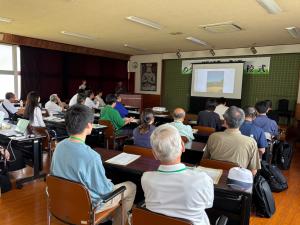
- 山間地域が抱える課題の解決や鳥獣被害対策の解決に積極的に取り組んでいただき、学生目線での考えを伺い、山間地域の現状を理解いただいてありがたいと思います。
- 過疎、高齢化が大きく進んでいる中で、故郷をどう守っていくか大きな課題ですが、今回、学生の皆様から提案を受け、まずは出来ることから少しずつ取り組めればと考えています。
- 今回、祝子川地区に足を運んでいただき、大崩山の大自然や清らかな川、山などを満喫されたと思います。これを契機に、ぜひ祝子川地区に再び足を運んでいただき、地域を盛り上げていただければと思います。ありがとうございました。
4.ロボットを活用した稲作支援研修
講師:株式会社テムザック 企画本部マネージャー 清水 鉄平 氏

≪ロボット活用稲作支援研修(講義)≫
≪ロボット活用稲作支援研修(農地研修)≫
- 北浦町古江地区におきまして、ロボットを活用した稲作支援研修を行いました。
- 山間地域での狭小な水田での稲作のコスト削減などを目的に、デジタル技術やソーラーパネルを活用したロボットによる稲作の取り組みの実証が進められています。
- ロボットを活用した耕起や水田の除草抑制、ドローンでの防除など遠隔から水田管理を行う実証により稲作の生産コスト低減の取り組みの実証が進められています。
5.「のべおか里山塾」開催予定
- 第3回「のべおか里山塾」
令和7年12月19日(金曜)~12月21日(日曜)
会場:延岡市役所、北方町、北浦町 他
(1)鳥獣対策基礎講座 (2)鳥獣対策特別講演 (3)ロボット稲作支援研修 他
- 第4回「のべおか里山塾」
令和8年2月14日(土曜)~2月15日(日曜)
会場:北川町 他
(1)鳥獣対策基礎講座 (2)くくりワナ仕掛け研修 (3)ロボット稲作支援研修 (4)森林整備体験 他
※のべおか里山塾のカリキュラムや会場、参加者募集等は改めて、お知らせいたします。多くの皆様の参加をお願いいたします。
【問い合わせ先】
延岡観光協会 電話:0982-29-2155
のべおか里山塾事務局(延岡市農林水産部林務課)電話:0982-22-7019 Fax:0982-21-6204
6.「のべおか里山塾」紹介動画
「のべおか里山塾」の紹介動画及び農林水産省BUZZMAFF(ばずまふ)での紹介動画がご覧に頂けます。
https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/39/42410.html
※BUZZMAFF(ばずまふ)とは、農林水産省の職員自らがYoutuberとなって農山漁村を訪れ、農林水産業の魅力発信を行うプロジェクトです。(農林水産省ホームページより)
※このBUZZMAFF(ばずまふ)は、令和7年2月に開催されました、令和6年度第4回「のべおか里山塾」が取り上げられています。













