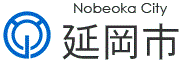
延岡市携帯サイト
昭和43年に年賀郵便切手の絵柄として採用され、昭和59年には宮崎県伝統工芸品として認定を受けた、江戸時代から伝わる郷土玩具です。
風を受け、張り子の猿が踊る様はたいへん可愛らしく、5月の節句に子どもの健やかな成長と五穀豊穣を願って、鯉のぼりと一緒に庭先に立てた城下町延岡の風習を今に伝える一品です。
 ?
?
〜どうして「のぼり猿」が作られるようになったの?〜
この紙芝居は、のぼりざるフェスタ実行委員会メンバーが、のぼり猿製作所「松本」の商品説明資料「のぼり猿由来について」をもとに作成しました。(「のぼり猿」の由来については、この紙芝居でご紹介した以外にも、いくつかの説があります。)
のぼり猿は、子どもの立身出世や無病息災、五穀豊穣の願いをこめて、江戸時代から受け継がれてきたものです。
現在では、その名称が、市内で開催されるイベントなどにも使用されています。また、のぼり猿をモチーフにした図柄やキャラクターを、普段歩いている道路などでもたくさん見ることができます。例えば、マンホールの蓋や道路標識など、いろんな場所にのぼり猿が描かれています。
このように、のぼり猿は、延岡のまちにとけこみ、市民の皆さんにとって身近なキャラクターにもなっています。